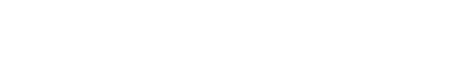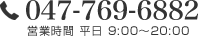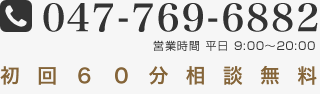養育費
1 養育費とは
養育費とは、未成熟子が社会で自立をするまでに必要とされる費用のことです。未成熟子とは、成人年齢とは関係なく、まだ経済的に自立できていない子を意味する法律用語です。高卒で18歳でも就職して経済的に自立できれば。未成熟子ではなくなります。他方,満20歳を過ぎて大学等に進学している場合は,経済的に自立していないとして満22歳に達した後の翌年3月(大卒時)まで養育費が認められることがあります。
なお,成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案が参議院本会議で成立し,衆院法務委員会で可決されました。2022年4月1日から施行される予定です。そうすると,養育費の支払期限を成人までという言葉で今契約した場合,18歳で打切か20歳かで争いになる恐れがあります。公正証書の場合,20歳とか大卒に相当する22歳と明記していることが通常ですが,この点は今後注意すべきことになります。
2 請求に関して
離婚の際,未成熟子を引き取って養育することになった親の方から,もう一方の親に対して養育費を請求することになります。養育費という言葉は,民法に直接記載されているわけではなく,婚姻費用分担(民法760条)、夫婦間の扶助義務(民法752条)、子の監護費用(民法766条1項)の条文が養育費の根拠になります。
3 養育費の額
養育費の額については,離婚する父母の間の合意(協議)により決められますが,強制執行可能な公正証書にしておくことをおすすめします。離婚後養育費に関してのみの調停や審判をする場合と離婚訴訟の付随的な請求として養育費を定める場合があります。裁判所は,養育費の算定表を公表していますので,その算定表に従った判断がなされることが通常です。算定表はインターネット上でも見ることができます。
ただし,算定表による金額には一定の幅がありますし,個別的事情から,増減がありえます。
4 支払い義務
原則は,養育費の支払請求がなされた時から,子どもが成人(20歳)になるまでの間,養育費の支払義務があります。大学進学等の場合は別途両親間で協議される場合もあります。更に,医学部卒とか大学院卒までという決め方も出来ます。ただし,これは,養育費という概念から外れますし,裁判手続でそこまで認められることはないと思われます。
5 支払い方
養育費は,分割払いが原則です。通常1か月当たりの金額を定めて,子どもが20歳になるまで毎月末又は○日までに支払うと定めることになります。
6 公正証書
養育費の額・支払方法について協議が成立している場合は,これを書面にしておくべきです。そして,将来の支払いを確実にするためには,強制執行できるように公正証書にしておくべきです。
7 調停
離婚が成立していない場合は,離婚調停の中で養育費の額もあわせて定めることになります。すでに協議離婚が成立しているような場合には,養育費の支払いを求める調停を申し立てることになります。
調停が成立しない場合は,審判・訴訟へと移行することになりますが,適切に手続きを進行させるため,なるべく早い段階から弁護士に相談し,処理を委ねることが望ましいでしょう。
8 養育費の変更
養育費は幼児期から成人まで長い期間の取決めになる場合が多いので,事情が変わった場合,元夫又は妻から養育費の増減額の請求をすることができます。
養育費を受け取る権利を有する親の収入が増加したとか,養育費の支払い義務を負っている親が再婚して新たに子どもをもうけたような場合,養育費が減額されることもあります。これらの場合,養育費の変更を求める調停を申し立てることになります。